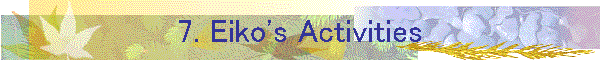
|
|
|
�N���X�ł̊����𒆐S�ɂ��Ă��܂����A���{�����₢���ȏЉ�̂��˗������������ƁA�ǂ��܂łł��o�����܂��B��ƁA�������A�w�Z�APTA�A�c�̃O���[�v�ȂLj˗���͂��܂��܂ł��B�G�߂̐A���ɂ܂��b�Ɏn�܂�A���{�l�̐S�ɘb�������Ă����͓̂��ӂł��B�����͎В������͂��Ďd�グ��Ƃ������C�x���g�̂��˗��������������Ƃ�����A�������F�A������Ă��܂��B Eiko's activities don't remain within the regular classroom. Requests come from outside from time to time. Some of them require participation of myself as well as supports of the other members in the class in a group work. In such cases, the whole of the class work together hard in pleasant excitement.
<February 2013: The lecture and a workshop at the Hiroshima International Students House> sponsored by Hiroshima International Women's Club
Thanks to the HIWC ladies, my class ladies and all participants, we were able to have an enjoyable day!
<November 2012: The workshop at the University of Michigan, Detroit USA> (Now working. Please wait for a while.) The activities I did in Michigan was reported in 'Detroit Japan Newsclub'
�@�@
<October 2012: The lesson for the spouses of the participants of SIBOS 2012 taken place in Kansai, Japan> �����ŊJ�Â��ꂽ�T�C�{�X2012�Q���҂̔z��Ҍ����@���b�X���� sponsored by TYA Culture Salon
�@ �@
Well done for the first ikebana arrangement!
Thanks for your supports!
<February 2011: the publication "Japanese Culture as seen in Ikebana"> 2011�N2��17���@�����w�����Ȃɂ݂���{����--�������ꂽ�Ԃ̗��j�x�i�v���t�o�ŁA�ō�2730�~�j�����s����܂����B �u���T�A�����O�̕���Ώۂɂ����ȃ��b�X�������Ă���ƁA���{�l�Ə��O���̕��X�̉Ԃɑ���v���ɂ́A���{�I�ȍ��ق�����ƋC�t�����B�������A���ꂪ�����͂킩��Ȃ������B�@�i�����j�@�q�����������������̂��@�ɁA�{�i�I�Ɍ������n�߂��B���ׂ�Β��ׂ�قNj^��͗N���A�܂��A���ꂪ�ʔ������������B�ǂ��܂Œ��ׂĂ������͐s�����A�C�����Ύ��͔��m�_���ɒ��肵�Ă����B�v�i���Ƃ������j ��������10�N�Ԍ������Ă������ʂ��܂Ƃ߂��̂��{���ł��B�A������ɓI���i���ė��j���T�ς��A�A������̐��܂ꂽ�w�i�𐄑�����̂́A������̂悤�Ŗʔ������̂ł����B�����ɂ͓��m�N�w�Ɛ��m�N�w�̈Ⴂ�������Ă��܂����B���e�̊T�v�͉��ɏ����܂��̂ŁA�����̂�����͌䗗�ɂȂ��Ă��������ˁB
e-mail�ŏo�ŎЂɒ��ڂ��\�����݂��������̂��ȒP�ł��@pub@shibunkaku.co.jp�@ �v���t�o�Ŏ��@�@���@075-751-1781
<August 2010: at the Beijing University in China> ��2010�N8���F�k����w�ɂā��@ ���۔��w���18�E���ɉ����ăp�l���f�B�X�J�b�V�����u���{�̔��v�̃p�l���X�g�����܂����B�ʐ^�͊�u�������Ă���l�q�ł��B�����Ȃɗ����u���̂���厖�ɂ���C���v���u�������v�Ƃ������{��Ő����B�����̓��ӂƎx�������������E�C�{���B The 18th International Congress of Aesthetics was held at the Beijing University. In the Panel Discussion on �eJapanese Aesthetics�f in the congress, I gave a presentation titled "The Key Underlying Value of Ikebana--IKASU". I was one of the four panelists that included three famous scholars. I pointed out the importance of treasuring LIFE of living things by introducing a Japanese word "IKASU". I explained that "IKASU" means bringing out full potential of everything. I further explained that, in order to realize "IKASU" in an Ikebana arrangement, the arranger needs to try to show each plant in their best. I am happy to
report that my presentation was favorably received. I think I was the first speaker who made a presentation on Ikebana
academically at the International
Congress. I
am most pleased that Ikebana has become a subject to be
included in an academic discussion in the prestigious forum like this.
<May 2010: The lesson on the Clipper Odyssey, cruise ship from America> <2010�N5���@�A�����J����̃N���[�Y�D�N���b�p�E�I�f�b�Z�C�@�D��ł̃��b�X���� I was asked if I could give a hand-on lesson of ikebana and calligraphy to the guests of the ship. There was only two weeks before they would arrive at Hiroshima! Luckily I had a licensed calligraphy instructor in the class. So I made a team 'the Clipper Odyssey project' with some of my students. I knew that our team was very strong and would work very powerfully toward the set aim.
Now finished successfully!
A report of the trip to Australia <March 2009: A Visit to Ikebana ladies in Melbourne>
Congratulations, Rosemary! I like your sense of humor that you call your class 'Sparrow School'. I will come and support your exhibition!!
and thus I visited Melbourne with some ladies from Hiroshima. The season in Melbourne was the beginning of autumn. I gave a talk on the spirit of Ikebana and demonstrated a small arrangement.
~Sparrows' arrangements~ Most materials were from Rosemary F's garden. I had worried about damages on the plants from bushfires which had been reported about. Luckily, they had rain on the previous day we arrived. I was glad to find greens there look fine.
~~We all enjoyed the event from the preparation to the dinner~~
It became like a reunion for those who had lived in Hiroshima.
Now we live in different places such as Melbourne, Mexico-city, Chiba and Hiroshima. We all, however, gathered with a immediate decision of the trip when we heard of the word Ikebana. I realize that Ikebana keeps our friendship close!
~~ We also enjoyed every minute during the preparation for the exhibition ~~
I saw some of them for the first time after they left Hiroshima around 20 years ago!
��May 2008:�g�[�X�g�}�X�^�[�Y�S�����ɂču���@Talk at the Toastmasters International All Japan 2008 Spring Conference�� �g�[�X�g�}�X�^�[�Y�S�����L�����ۉ�c��œ���Ԃɂ킽���ĊJ�Â���܂����B���̓Q�X�g�u���𗊂܂�A�В�������̉Ԃ�Q�X�g�̃R�T�[�W��������˗�����܂����B�X�s�[�`�R���e�X�g�ł͓��{�ꂪ�I�o����A�p��̕��̏��҂͉ẴJ�i�_�ł̐��E���ɃG���g���[�Ȃ����܂��B�ǂȂ������^���ŁA�M�C���`����Ă�����ł����B�听���̑��ŁA��ւ�������������G�L�T�C�g�����C�x���g�ł����B
��April 2008:�ԓW�u�����Y Lectures in Takeo, Kyushu�� ���ꌧ���Y�̉���z�e���ŁA����������̒��x�e�����搶��5�����ԓW������܂����B���Ԓ��̃C�x���g�Ƃ��ču����J�Â���u��炵�ɉԂ��v�Ƒ肵���b�������Ă��������܂����B��ɂ���A�����_�C�i�~�b�N�ɉ����Ɏ������܂�A�搶���̑����������܂��i�ƂȂ��Ă��܂��B������̍�i�ɂ��u���Ԃ̌o�߁v�Ɓu���̂��v�������܂����B�������܂����̂ł��̂܂܂��b���邱�ƂŁA�u���������ɐi�݂܂����B3�������Ă̍u����͏��߂Ă̌o���ł������A�������2���ځA2���ڂ��3���ڂ����O�̐��͑������A�ԓW�̐������`����Ă��܂����B����������̐搶���A�����l�ł����B �@
�@�@
��April 2008: Invited by Ikebana International Hong Kong�� �C�P�o�i�E�C���^�[�i�V���i�����`����̂��������Ń��[�N�V���b�v�������Ă��������܂����B�C�P�o�i�E�C���^�[�i�V���i���́A���h�ɂ������Ȃ��A�C�P�o�i���D�Ƃ����̏W���ł��B���`�̈��D�Ƃ����ɁA���̗��h�̂��Љ�ƃ��b�X�������܂����B�В�����5�����������s������A���[�N�V���b�v�����邱�ƂȂ���A�������ɂȂ������Ƃ͌����܂ł�����܂���B�y�����v���o��1�y�[�W�������܂����B
�����̗l�ɃC�P�o�i�̐��_�̐�������
�@ �f��������
�F�l����i����
�C�Â������Ƃ��蒼�������Ă�������
�A�[�@�I���܂����I
��November 2007: �@Appearance in the NHK TV program�� �C�O��NHKTV�ԑg�u�r�M���@�W���p�m���W�[�v�ɃQ�X�g�o�������Ă��������܂����B���{���Љ��30���Ԃ̉p��ԑg�ŁA�u�g�t�v�Ƃ����e�[�}�ł����B10�����{�A���c������قŎ��^���Ă��܂����B�O���A�g�t�̍�i���삢�����݂܂����B�����A�g�t�͌͂��O�̗t�ł�����A�����A�����オ�炸�����Ⴍ����ɂȂ��Ă���}��������Q�āB���āA�{�Ԃ́A�����̃J�����E���C�g�E�l�X�̖ڂ̑O�ŃC�M���X�l���y�]�_�Ƃ̃s�[�^�[�E�o���J������A�A�V�X�^���g�����f�B�I������ƁA�g�[�N����Ƃ������e�ł����B�t���A����́u�S�C�R�C�Q�E�E�v�A�u�P�Ago�v�ɂȂ�ƁA���̓��͐^�����B�u����H�@���A�����������H�v�u���߂�Ȃ��`���v��NG�����x���o�������̂ł��B�ł��A�ҏW����Ďd�オ�����ԑg�́A�Ƃ��Ă��X���[�X�B�g�t�̔��������A�a�́A�G��A����Ȃǂ�ʂ��ďЉ�A���{�l�̍g�t�ɕ����N�w���A����͌����ɕ\���Ă��܂����B�������ANHK����ł��I�@�S���͂��Ƃ��A���E���ŕ�������A�u���܂�����vmail�����X�ɂ��������܂����B�N���X�̊F�l�̂����͂��傫���A���ӁA���ӂ̏o�����ł����B
�@
<November 2007 & March 2008 : Lectures at an Ohara School Branch > �����������ȍL���x���̂��˗��ŁA2007�N11���A2008�N3����2��ɘj��A�u�����������Ȃ�m��v�Ƃ����e�[�}�ōu�������Ă��������܂����B���i�̊������Ԃ⏔��y�搶������u���Ƃ���A�����̍u����Ƃ͏��肪�Ⴂ�܂������A���̎v�z�ɂԂ�͂���܂���B�����Ȑl�Ƃ��āA�����Ȃ̎Љ�I�����ɋC�t���Ă���������Ƃ̎v���ŁA��点�Ă��������܂����B�����������z�[���y�[�W�̍L���x�������̂Ƃ���ɁA����ȕ��ɏЉ��Ă���̂������܂����B http://www5e.biglobe.ne.jp/~ohara-h/katudo/H19/kouenkai/kouenkai.html http://www5e.biglobe.ne.jp/~ohara-h/katudo/H20/ikebanasi2/kouenkai.html�@
��February 2007: �@Invited by the Foreign Correspondent's Club Japan�� �O�����h������ōu�����˗�����A�L�y���ɍs���Ă��܂����B�����Ȃł̔��m�w�ʂ��擾�����͎̂������߂Ăƕ����ꂽ�A�����J�l�L�҂���̂��b�ł����B�������ە���ł́A�������ɋْ����Ă��܂��āB�B�B�@�ł��A�����Ȃ̐S�𐢊E�ɔ��M�ł���D�@���Ɗ�����������܂����B
������ƁA���낵���`���ł��ˁB�B�B�@�@�p�������f�X�l�G�B �@
��November 2005:�@Interpretation of the lesson by the INTERFLORA World Cup Champion�� ���N�x�t�����[�@���[���h�@�J�b�v�D���҂�Per�@Benjamin���i�X�E�F�[�f���l�j�������ẮA�u�K��L���ŊJ�Â���܂����B���͒ʖ�������Ă��������܂����B�~�Ɍ����āA�X�Ɛ���C���[�W������i�����X�ɕ��т܂����B
�@
��April 2005:�@Lecture at the alumni association�� �u�����Ȃɂ݂���{�l�̔��ӎ��v�Ƃ����e�[�}�Ř_���������n�߂āA�������N�ɂȂ邩�B���݂́A�|�p�w���m���̎擾��ڎw���āA�V�R�V�R�_���������i�߂閈���ł��B�]���ւ���Ă����������������A�����ȂɊւ��邱�Ƃ����ɍi���Ă��܂����B�ŋ߂́A�����ɂ܂��u���̈˗������������悤�ɂȂ�܂����B ����́A������Ō������\�����Ă������������̎ʐ^�ł��B���̂Ƃ��̑�́u�����Ȃ̎Љ�I�������l����v�B����܂Ō������Ă������Ƃ��A�Љ�I�Ӌ`�Ƃ������ʂ���܂Ƃ߂Ă݂܂����B�p���[�|�C���g�ŁA�����̉摜�����������Ȃ���50���B�t���A����̎��������A�������܂��܂��B�܂��A�E�C�����������āA�����ɐ��i����G�l���M�[���łĂ��܂����B
�@
��September 2003: at the Hiroshima International Women's Club �� A speech at a general meeting of the International Hiroshima Women's Club by Mr. Akiba, the Mayor of the Hiroshima city, was canceled due to mayor's urgent business. It was five days before the day and I was asked to give a talk as a substitute lecturer for him. Gee..... five days.... 'Be calm, Eiko. I still have five days.' I encouraged myself and got concentrated to prepare the talk with 76 pictures on Power Point program. I barely made it! Hiroshima International Women's Club��9�����ŏH�t�L���s�����Q�X�g�X�s�[�J�[�ɂ��}������\��ł����B�Ƃ��낪�A5���O�ɂȂ��ċ}�ɂ���������Ȃ��|�̘A���������������ŁA��ň˗������̂Ƃ���ɔ�э���ł��܂����B�Q�Ă܂������A���v�A�܂�5������B�B�B�@�}篎v�����āA�p���[�|�C���g��76���̉摜�����������Ȃ���A�����Ȏj��b���A���̌�A�f����3�삵�܂����B���傤�ǁAC����͂��̓����Ō�ɗ����Ȃ���\��ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�ޏ��Ƀf����i�̎�`�������Ă��������ȂǁA�����@��ɂȂ�܂����B���Ƃ���ł̓Z�[�t�B�B�B�@���������B�@ �@
�@ �@
��2002�N11��10���@�L�����������k�i������������ �L�����d�v�������ł���k�i�������قŖM�y�A����Â̖��Ȋӏ܉����܂����B���̕���������ʌ����̉��Ƃ��Ďg�p�ł���̂͏��߂Ă������ł��B�����͑����̓�Ԃ��g���̂ŁA���̊Ԃ��ꂼ��ɉԂ�������悤�ɂƂ̈˗������������܂����B�d���Ȃ�ł̖͂ʔ����o���������Ă��������܂����B�Ȍ�A2010�N���݂܂ŁA���N�����ĒS�������Ă��������Ă��܂��B �O�����āA��������҂̖��O�A�A����ȂǍׂ���������A�����������Ȃ��l�ɁA����H���Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA���x�����ӂ���܂����B�����̂��߂ɊW�҂������ł��鎞�ԑт͑O��3������ŁA5���ɂ͊��S�I�����ďo�傷��悤�ɂƂ̂��ƁB �ՂȂNJy�������3������ƕ����܂����̂ŁA���ז����Ȃ��悤�Ɏ��͎��Ԃ����炵��4������s���܂����B������Ƃ����悤�Ə��̊Ԃɋߊ���Ă킩��܂������A�d�C���Ȃ��̂ł��B���̓��́A�����̓܂���ł����̂ŁA���Â���ł̍�ƂƑ�����܂����B5���܂łɏI���Ƃ����̂́A�ّ��̗v���Ƃ�����蕨���I�ɕK�v�������̂ł��B����ɂ��Ă����̊Ԃ̍�i����1���Ԃŏ��������ЂÂ��܂łƂ����̂́A������Ƃ������̂�����܂����B �����͏��t���a�ʼn����ł����B��q��t�X�}���͂����đ傫��������������H�̕�����ς��̒낪���߂��܂����B��џ��̏�ʼn��t�����ՁA�O���A�ڔ��̉��ƏH�̋�C�ɁA���̐̂̋C���ɐZ���ґ�ȂЂƎ��ł����B �@
�@ �@
�@ ��2002�N1���@�L���s���w����ف@�ٕ��������u���� �L���s���ی𗬃Z���^�[����̂��b�ŁA�u�����Ȃɂ݂���{�l�̔��ӎ��v�Ƃ����e�[�}�ŗ��w���A�s����Ώۂɂ����u�����J����A���͍u�t��w�߂܂����B���w����يْ��͂��߁A�X�^�b�t�̊F�l�A�Q�����Ă����������F�l�Atea�@time�ɂ͂��َq���Ă��ĉ������搶�A�r�I�����t���ĉ����������c���v�ȁA����Ƀ��b�X������`���ĉ����������k�̊F�X�l�̂������ŁA�Q���ґS�����y���������߂����܂����BNHK�e���r�A�����V���A�����V���A�^�E���������ނɂ��Ă�������A�G�L�T�C�e�B���O�ł����B�����ʂ�A�Ԃ��������Ă������������́A������Ƃ����C�����B���ӂł��B �����V���L���u���{�l�̔��ӎ���̌��@���w���琶���Ԋw�ԁv���C���^�[�l�b�g�@�A�T�q�R���ɁA�ʐ^�ƂƂ��ɐ����Ԍf�ڂ���Ă��܂����B�����ł́A����ꂽ���ԓ��ɓ`����Ȃ������ƒW�����������܂������A������Ɨ������ĉ������Ă���L�҂Ɍh���ł��B�ȉ������V���̔����ł��B�i2002�N1��28���j�@ �@�@ �@����܂��A�����Ԃ̗��j�╶���ɂ��ču���B�@�u���{�͐��m�ƈႢ�A�s���S�Ŕ�Ώ̂Ȕ����ɂ��A����Ȃ������𐄂��ʂ�w�@���̕����x������v�ȂǂƐ��������B�@����ɗ����̎����ɍ��킹�āA�Q���҂��l�R���i�M��̉ԂȂǂ��g���A�����Ԃɒ��킵���B�@�C���h�l�V�A�o�g�̃v�g�D�E�A�O�X�e�B�i����i�R�S�j�́u�����̉ԂōL�����\������Ƃ��낪�����ł��v�Əo���h���ɖ������B�����́u�@����Ƃ������{�l�̔��ӎ����A�v�����̐S�ɂȂ��邱�Ƃ�m���Ă��炦��v�Ƙb���Ă����B
���F2002�N1��28�������V�����@�@�E�F�����̐��k������A���b�X������`���Ă��������܂����B �@ �@
2001�N6���@�L�����w�@��w���ƕ��i �����S����҂����ɓ��{���������Ƃ��A���Z�����������܂��B �@
�@ �@
1999�N�W���@�Ђ낵�܍��ۃZ���^�[�ɂāB�L��������ALT�i��w����A�V�X�^���g�j��ΏۂɊJ�Â��ꂽ�ċG�W���u���B��͓��{���������N���X�S���BOHP�ɂ��ʐ^���g���ē��ӂ́u���{�l�̌��_�v�ɂӂ�Ȃ���̍u�`�Ƃ����ȃ��b�X���B �@
�@
99�N4���@�C���^�[�i�V���i���@�E�[�}���Y�@�N���u�ł̃f�����X�g���[�V�����B�L���O�������B�A�z�e���ŊO���w�l�Ώۂ̌����ŁA�u���b�c�@�G���W���C�@�C�P�o�i�v����B�܂��͐��ƃX�C�g�s�[���Ă����B�����Ȃ���A�킹�Ȃ���A�J�����Ƀ|�[�Y���Ƃ�Ȃ���B�t�[�E�E�E�A��ςł��B �@ �@
�@
�@�@98�N�@�}�c�_YFU�X�J���V�b�v�@�v���O���� �@�C�O����̊w���ɂ����Ȃ��Љ�B�w�������̑؍ݒ��̎v���o���܂Ƃ߂����q������ƁA�����̊w�����C�P�o�i�̌��������Ă��܂��B���Œ����Ă���̂��킩��A����������ł��B �@ �@ �����������ȋ�������ʉ���E�|�p�w���m�@��@�Ďq �@ �����₢���킹�F�����S�ԉ��i�L���s�����j�@Tel�F082-221-3515 �R�����g�@mail�F�@eiko@hbs.ne.jp �@ page end |